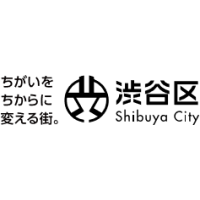新しいホームページになりました!
渋谷区立神南小学校のホームページへようこそ!
令和8年3月31日(火)まで、旧ホームページから新しいホームページへ転送されます。
新しいホームページのお気に入り、ブックマークの更新をよろしくお願いします。
携帯、スマートフォンの方は右上の ≡ をタップするとメニューが開きます。
ボランティアを募集しています!
☆児童の学習や生活面での支援 ☆通訳(中国語・モンゴル語)
※大学生の方、社会人の方(現神南小学校保護者の方はご遠慮願います)が対象となります。現保護者の方でお知り合いの方がいましたらご紹介ください。
令和7年度入学予定者向け
7年度入学予定者向け 新1年保護者会を実施しました。
欠席された方は、神南小学校までご連絡ください。(代表TEL 03-3464-0659)
新着配布文書
対象の文書はありません